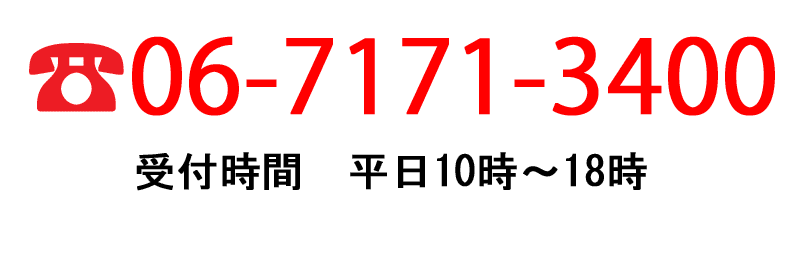
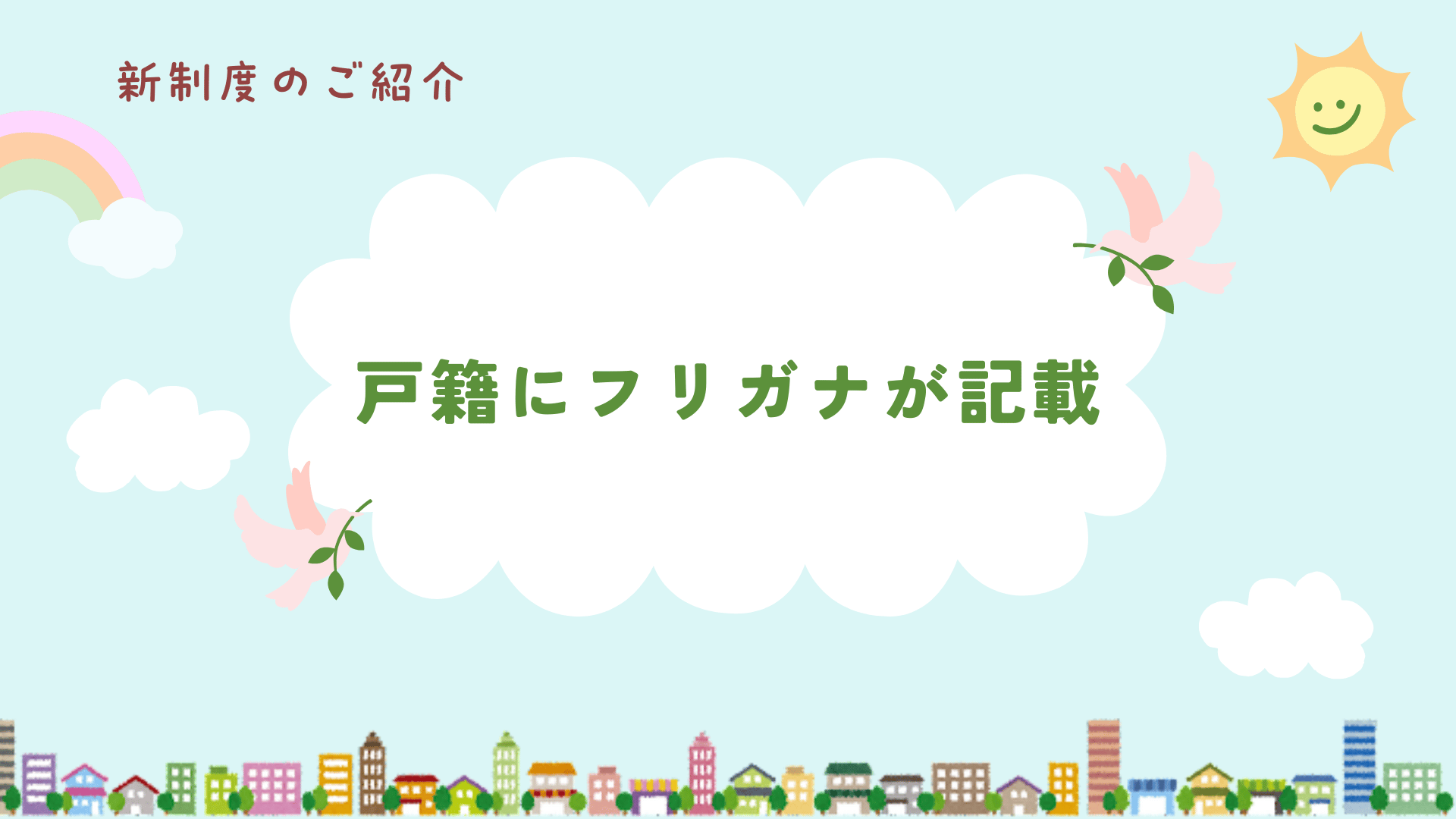
 司法書士大藤
司法書士大藤司法書士の大藤です。
抵当権抹消手続きに関連する情報をご紹介したいと思います。
こんにちは、不動産名義変更専門サイトの北摂リーガルオフイス大藤です。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
その改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されます。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
登録に関しては、今後出生する赤ちゃんだけではなく、全国民が登録することになります。
皆様も必ず登録されることとなりますので、ご留意ください。
<法務省からお知らせ動画>
今回の戸籍フリガナ制度。
本音としては、キラキラネームなど読めない名前が増加したことへの対策だとは思います。
が、キラキラネーム防止で法律作りましたとも言えないので、一応、制度趣旨としては、以下のように述べてます。
1.行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されている。
しかし、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に手間暇がかかっていた。
そこで、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになる。
2.本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになる。
正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなる。
3.各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがあった。
そこで、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができる。
さて、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりますが、その流れを見てみます。
本籍地の市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載するわけですが、
事前に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
この通知は、令和7年5月26日から順次発送されるようです。
そして、内容を確認し問題なければ、何もしないでいいです。
そのまま通知通りのフリガナが戸籍に記載されます。
通知にあるフリガナに謝りなどがある場合は、次のSTEP2「氏名のフリガナの届出」をすることとなります。
通知されたフリガナに謝りなどがある場合。
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
なお、
通知されたフリガナが正しい場合には、何もしなくていいです。
制度開始から1年経過後に、そのまま通知通りのフリガナが戸籍に記載されます。
STEP2「氏名のフリガナの届出」がなかった場合は、事前通知通りのフリガナが戸籍に記載されます。
STEP2「氏名のフリガナの届出」の具体的な方法について。
<氏>
苗字(氏)のフリガナに謝りなどがあった場合は、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
ただし、死亡などで筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届け出をする。
配偶者がいない場合や、配偶者も除籍されている場合は、その子が届け出をする。
<名>
名前のフリガナに謝りなどがあった場合は、本人が届け出をする。
これは当然ですね。
他の人が勝手に届け出できたら大変です。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
また、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能。
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られる。
ただし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重することとしている。
たとえば、「神田」という苗字を一般的な読み方である(かんだ)ではなく、(しんでん)と読んで現に使用してる場合には、その読み方を尊重するということです。
ただ、その場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この書面の具体例としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されてます。
逆に言えば、パスポート等において既に使用している氏名のフリガナと戸籍上の氏名のフリガナと違っていると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなどの不都合が生じる可能性がありますので、違いがないように手続きを忘れないようにしておくべきだと思います。
なお、今後出生した子供については、最初からフリガナを登録することになります。
この場合、「氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているもの」
という制約が課されることになります。
法務省によると、認められないケースについて、「高」(ひくし)、太郎(じろう)、太郎(ジョージ)などがあるそうです。
法務省は「高」(ひくし)は反対の意味であること、太郎(じろう)は読み違いかどうか判然としないこと、太郎(ジョージ)は関連性が認められないとしています。
以上です。